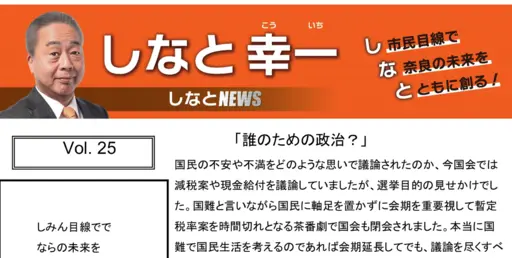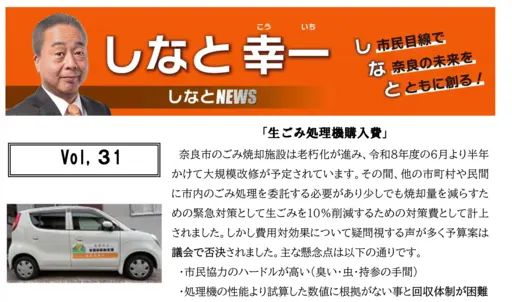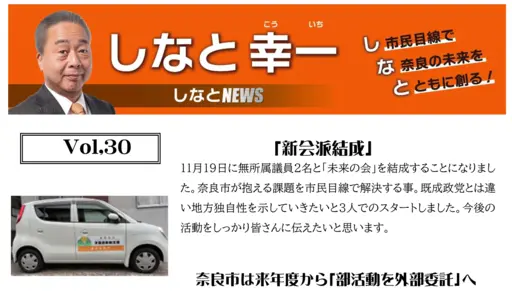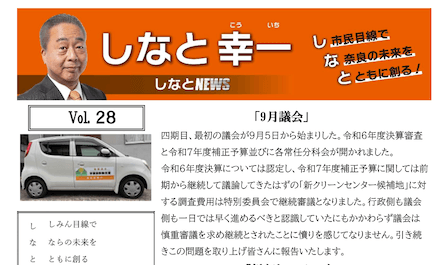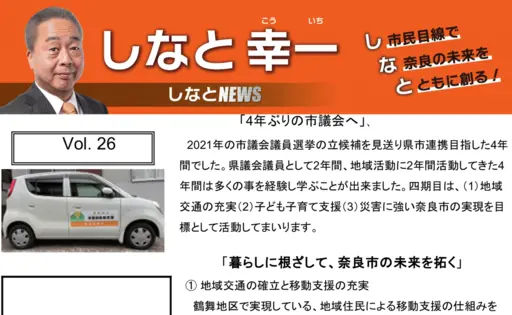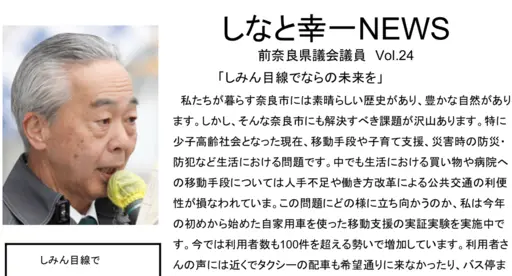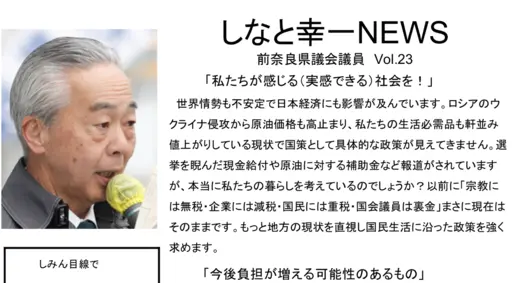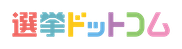誰のための政治?(しなと幸一 NEWS Vol.25)
「誰のための政治?」
国民の不安や不満をどのような思いで議論されたのか、今国会では減税案や現金給付を議論していましたが、選挙目的の見せかけでした。
国難と言いながら国民に軸足を置かずに会期を重要視して暫定税率案を時間切れとなる茶番劇で国会も閉会されました。本当に国難で国民生活を考えるのであれば会期延長してでも、議論を尽くすべきと考えます。
地方議会では議論が尽くされなければ会期を延長する事はよく耳にします。しかし国会では、通常国会(常会)は1回、臨時国会や特別国会は2回まで延長できますが、延長には衆参両院の議決が必要との事で、今回も国民目線でなくご都合主義で問題解決することなく国会を閉じてしまいました。
「地域の困りごと」
少子高齢社会となり、何気ない日々の生活でも困り事が増えています。生活の足となる移動支援では暮らしの買い物や通院の手段を地元で解決しました。今後は継続できるよう関係団体との連携を築いて行きます。
また、日々のゴミ出しについても各地域で共通の課題となっていて、福祉協議会などで提案されていて、今のゴミ収集時間は生ごみについては遅いところで午前8時までとなっていて、高齢者の方では時間内に出すことが困難でごみ屋敷になりかねません。
先日の意見交換会では、ゴミステーションが坂道の上で運ぶのが大変、自身のゴミを近所の方に出してもらうのは気が引けるなど地域ならではの問題が多く聞かれました。解決方法として行政のゴミ収集時間を、せめて午前中に変更してもらえればヘルパーさんなどの協力で解決できるので行政との調整を行って行きます。
「中学校のクラブ活動」
奈良県と奈良市では、中学校のクラブ活動(部活動)を「地域クラブ活動」へと段階的に移行する方針を打ち出していますが、それぞれに特徴があります。 奈良県の教育委員会は、休日の部活動を地域クラブ活動へ移行する方針を明確にしています。令和6年3月に発行された「中学校部活動の地域クラブ活動への移行の手引き」では、以下のようなモデルを提示しています。
- 行政主導型:市町村が中心となって運営
- 総合型地域スポーツクラブ型:既存の地域クラブを活用
- 拠点校型・単一クラブ型:特定の学校やクラブが中心
- 大学・企業連携型:外部資源との連携を重視
この移行は、教員の負担軽減と、子どもたちに多様な活動機会を提供することが目的と言われていますが受け皿となる地域クラブが充実しているのかの検証が必要です。奈良市の考え方も県の方針に沿って、独自の検討懇話会を設置し、地域移行の具体化を進めています。 特に注目されるのは、地域のNPOや団体と連携した実証的な取り組みです。
たとえば、2025年には「NPOこどもゆめひろば」が奈良市立登美ヶ丘北中学校などと連携し、地域音楽クラブ・中学生吹奏楽団のプレ練習会を開催しました。 これは、2026年度からの本格移行に向けた試験的な活動で、地域の指導者が中学生とともに活動する新しい形を模索しています。
しかし、前段でも述べましたが、競技の種類や受け皿となるクラブチームの実態がまだ明確でない中、県の方針に従うことは生徒に対して負担が大きくなることが容易に考えられます。今後の教育委員会の動向を見ながら生徒に軸足を置いたクラブ活動のあり方を実現していきます。