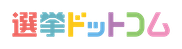「跡地の未来」を語ろう
米谷町への焼却灰搬入が令和7年度で契約期限が終了するため、
跡地を奈良市が購入・管理する予算が採択されました。
これは、単なる「処分終了」の報告ではなく、土地利用と環境再生の新たな幕開けと捉えるべきでしょう。
1. 歴史と地の条件を振り返る
過去50年間、米谷町は焼却灰最終処分地として使われ、市民に負担を引き受けてきました。
この土地の地形、周辺環境、インフラ条件を精査すれば、可能性は多様に広がるはずです。
周囲の住環境、景観、アクセス性、災害リスクなどを踏まえ、跡地活用の設計が必要です。
奈良市は2017年に米谷町で第2工区整備を行い、防災・環境対策を両立させた経験を持っています。(引用元リンク)
この経験を、今度は“跡地再生”にどう生かすか。
「終わりの整備」ではなく、「次につなぐ整備」へと発想を転換する時期に来ています。
この経験を、今度は“跡地再生”にどう生かすか。
「終わりの整備」ではなく、「次につなぐ整備」へと発想を転換する時期に来ています。
2. 跡地活用の方向性案
以下はいくつかの方向性案です(検討の入り口として)。
| 活用案 | 概要 | 利点と課題 |
|---|---|---|
| 緑地・公園化 | 自然地再生、親水空間、散策路 | 道路・水はけ対策、管理コスト |
| 都市型農業・コミュニティファーム | 地域参加型農園、環境教育 | 土壌改良・安全性の確保が課題 |
| 太陽光発電など再生エネルギー施設 | 資源循環と収益併存 | 出力制御、利害調整が必要 |
| 防災拠点・公共施設併設 | 災害時避難施設、地域集会所 | 用途の兼用設計と資金調達が鍵 |
これらの案を単発で議論するのではなく、
複数案を組み合わせた「ハイブリッド利用」も視野に入れるべきです。
3. 収益・維持の視点を忘れずに
どの案を採るにしても、初期投資と維持管理コストを無視できません。
公共予算・補助金・民間参画(PFI等)を含めた事業設計と、
持続可能性の担保が不可欠です。
米谷町跡地は、「過去の負荷」ではなく
「未来の資産」へ転換できる可能性を秘めています。
そこに息を吹き込むのは、行政と市民の共創です。
しなと幸一として、
皆さんと共に議論し、構想を形にしていきたいと思います。
しなと 幸一 (奈良市議会議員)